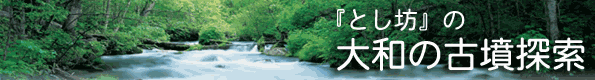
| ■石上神宮〜西大寺までの・・日本最古の道『山の辺の道』 ■ホーム |
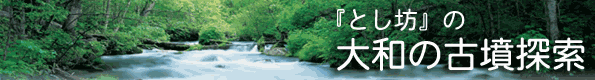 |
|
■春日山原始林(かすがやまげんしりん)・春日山原生林(かすがやまげんせいりん)は、春日大社の神聖なる山として、樹木伐採が千年以上に渡り禁じられてきたため、森林が極相に達した原生林が広がっている地域です。奈良市に近接して原生林が存在するのは極めて珍しいことから特別天然記念物に指定されています。特に春日山の照葉樹林は国の名勝にも指定されています。同時に古都奈良の文化財の一部として世界遺産にも指定されています。 |
 |
| 石上神宮〜崇道天皇陵の道 | 崇道天皇陵〜平城京の道 |
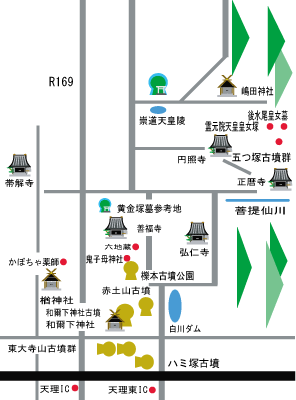 |
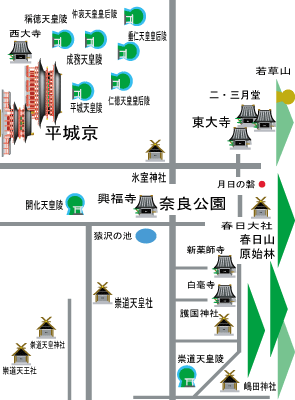 |
| No00■東大寺山古墳群 | |
| ■ハミ塚古墳 | ■東大寺山古墳 |
| ■シャープ天理工場敷地内にある東大寺山古墳群から移築した石室 | |
| ■名阪国道を隔てた北方には■ハミ塚古墳があり、天理市岩屋町で確認された七世紀初頭の大型方墳がある。調査は行われていない。直径約10mの円墳が密集する群集墳の1つと考えられていたが県立橿原考古学研究所の発掘調査で東西約49m、南北約44.6mの規模の方墳とされた。この時期は蘇我氏が全盛期を迎え、蘇我馬子の墓とみられる同県明日香村・石舞台古墳も大型方墳であることから、大和の方墳は蘇我系との見方があったがハミ墳は蘇我氏と対立していた物部氏の本拠地にあり、終末期古墳の研究に再検討を迫る結果となっている。また、同じく平野部との比高差約70m丘陵上に位置したところには■東大寺山古墳がある。規模・形状は推定約140mの前方後円墳で憤丘には円筒埴輪を巡らしている。後円部の埋葬施設の主体部は、憤丘主軸に平行する木棺を覆った粘土槨があり、長さ推定約9.4m大規模なもので、主要部分は盗掘を受けている。粘土槨の東西に墓壙が掘られ豊富な武器や武具が副葬されてい。その東側の墓壙から24文字を金象嵌で刻み「中平」紀年銘を持つ鉄刀が出土。この古墳は天理市和邇から天理市櫟本にかけて和邇氏族の拠点であることから、関連の一族が築造したと推定されている。古墳時代前期・中頃にあたる四世紀後半に築造された前方後円墳である。■東大寺山古墳群に点在している丘陵には奈良県内で最大規模である、弥生後期の高地性遺跡があって東西約400m・南北約300mの範囲内に竪穴式住居があり、二重の空堀が巡っている。空堀の構造は大阪府和泉市の観音寺山遺跡に共通している。 ■中平とは後漢の霊帝の年号で184〜189年を指す「倭国乱」(『魏志』倭人伝)「倭国大乱」(宋書)が終結した時期。中平銘紀年刀は「倭国乱」終結後、後漢王朝から下賜されたものと考えられている。鉄刀に着けられていた環頭は鳥文飾り、内ぞりしていて日本の前期古墳に特有の直刀とは違い、中平の年号が示すように中国(後漢)製と言われている。 |
| No01■和爾下神社(わにしたじんじゃ) | |
| ■和爾下神社拝殿(左上)・柿本寺跡と石棺の蓋(左下)・北方から見る和爾下古墳(右下)) | |
| ■和爾下神社古墳は「延喜式」にもみえる古い神社で、もとは和爾氏(わにし)の氏神である。和爾氏は櫟本一帯を本拠地としていた古代豪族で、山城・近江或いは敦賀・伊豆方面にまで勢力を伸ばしていた。応神天皇(オウジンテンノウ)以後七代の天皇に后妃をいれ、葛城氏と並ぶ勢力をもっていた。その後も一族からは小野妹子・柿本人麻呂・小野篁(たかむら)・小野道風などの学者や文人が輩出している。祭神は天足彦国押人命(アマタラシヒコクニオシヒトノミコト)・彦姥津命(ヒコオケツノミコト)・彦国葺命(ヒコクニブクノミコト )といわれている。社殿は和爾下古墳の後円部の上に建つめずらしいもので、また拝殿前左右に寝牛の石像がある。本殿は檜皮葺き。彫刻や色彩がみごとな、桃山建築である【重要文化財指定】。ここ櫟本(いちのもと)は、柿本人麻呂の生地であると伝えられ、和爾下神社の西には歌聖。人麻呂ゆかりの歌塚が建っている。任地の石見国(いわみのくに)で死んだ人麻呂の遺髪を、後の妻である依羅娘女(よさみのおとめ)が大和に持ち帰り、この境内で葬ったと伝えられている。人麻呂崇敬が盛んになり歌塚としても有名になった。■柿本寺跡(歌塚)は当時、東大寺の末寺として、寺院の規模も大きく立派な伽藍が立ち並ぶ様子であった。延久二年(1070年)の興福寺雑役免帳東諸郡にも、寺名が記されており寿永二年(1183年)の『柿本朝臣人磨勘文』・「春道社の杜の中に寺あり柿本寺と称す」と記されている。現在も礎石が残っており、奈良時代の古瓦も出土している。大和文華館に保管されている柿本寺曼陀羅【重要文化財】は鎌倉時代の作。江戸時代には学僧が歌や茶道に親しんだ寺院であったが、明治初期に廃寺となった。また柿本寺跡には無造作に置かれた和爾下古墳から出土したと見られる、■石棺の蓋が置かれている。■和爾下古墳(わにしたこふん)は前方後円墳で古墳から石棺・埴輪円筒棺等が出土している。これらの遺物より築造時期は四世紀末から五世紀初頭とされている。規模は全長約120m、直径約70m、高さ約5mとされ、東大寺山古墳群を構成している。古墳から東北約800mに和爾の集落があり、この周辺一帯は古代大和政権の一翼をになった和爾氏の本拠地と推定されている。また、東大寺山古墳群は和爾氏の奥津城(おくつき・偉い人の墓)と考えられている。 |
| No02■赤土山古墳(あかつちやまこふん)・白川溜池(しらかわためいけ) | |
| 赤土山古墳 | 白川溜池 |
| ■赤土山古墳は東大寺山古墳群を構成する大型古墳。昭和六十二年から平成二年にかけて範囲確認調査が行われ平成四年度に史跡指定古墳となった。古墳の規模は残存長約103.5m推定では全長約110m程の古墳と思われる。墳形は測量成果から前方後方墳と考えられたが、くびれ部の形状が上下段墳丘とも前方後円状に区画されていたため、墳形の基本形態を前方後円形(変則的な造)とした。なお造り出しを後円部先端に築いており双方中円形にも類似している。築造時期は古墳時代前期末〜中期初頃の特徴をもつている。遺構については後円部の南側から南北約11m、東西約10mにわたり石敷があり、石敷き面の際には落ち込みに沿って並ぶ柱穴の跡がある。出土遺物は六世紀後半頃の須恵器破片が落ち込み付近から出土している。遺構の時期は出土遺物に須恵器(すえき)を伴うこと、埴輪列を切り込んで築いており、赤土山古墳の築造後に構築された祭祀遺構と考えられる。また後円部の南側から朝顔形及び円筒埴輪がほぼ原形のまま出土した。石製品の種類では腕輪緑色凝灰宕製鍬形石2点、緑色凝灰岩製石釧2点、玉飾り滑石製勾玉2点、滑石製勾玉16点、滑石製玉杖(杖頭部)、緑色凝灰岩製杖頭部品、緑色擬灰宕製管玉26点、緑色凝灰岩製玉杖(軸部)2点、その他緑色凝灰岩製合子(蓋)、滑石製品、緑色凝灰岩製合子(身)、滑石製刀子3点、滑石製剣、滑石製太刀、緑色溌灰岩製鍬、出土した遺物の中でも珍しい石製品は滑石製の玉杖形石製品である。形態的には琴柱形石製品にも類するものである。装飾には表裏が認められ、碧玉や緑色凝灰岩で造られていた。琴柱形石製品の古い特徴が認められ、杖などの頭部に取り付けた飾り付けといわれている。■白川ダム(白川溜池・しらかわためいけ)は一級河川大和川水系高瀬川の支川楢川にある、農業用の白川溜池(アースダム)の堤体を4.5m、嵩上げして堤高30m、堤体長516mに改築した治水ダムである。従前の農業用貯水容量86万立方m、および取水機能をそこなうことなく、新たに洪水調節をおこなうための、治水容量50万立方mを確保し高瀬川、楢川流域の洪水調節をおこなう。洪水調節はダム流域における日雨量204mmのとき、高瀬川の基本高水流量80立方m/sのうち55立方m/sを分流堰からダムに貯流し、25立方m/sを流下させる。また楢川の基本高水流量20立方m/sのうち、15立方m/sをダムに貯流し、5立方m/sを放流することで下流域の洪水を防げる。また、白川ダムは野釣りスタイルの釣り場でもあり、へら鮒の魚影濃い小型ダムとして多くの太公望に人気を誇っていたが、2007年の調べでは、鯉やブルーギルなど外来種も増え続け、なかなか以前のように、へらぶなが釣れるとはいかないようである。ポイントは全て護岸されているので、釣台は必需品てある。ダム周辺はきれいに環境整備されていて、ダムの東側には東海自然歩道(山の辺の道)が通り、周辺は古墳公園や一般公園にもなっている。 |
| No03■櫟本(いちのもと)高塚古墳公園 | |
| 櫟本高塚古墳公園 | 鬼子母神社(きしもじんじゃ) |
| ■櫟本高塚古墳公園は自然に恵まれた敷地と変化に富んだ地形を利用し、六世紀後半の櫟本高塚遺跡等の地域の資源を活用した、古代ロマンとのふれあいを想像することが出来る公園。この公園の周りには古墳時代の大型前方後円墳が多数あり、東大寺山古墳群と呼ばれている。公園の施設は遊技広場・多目的広場・遺跡の丘・小広場・休憩広場等がある。発掘調査で古墳時代の柱穴の跡が見つかっており、建物跡の形や規模から特殊な建物跡と思われ、盆地を見下ろせる丘陵に造られた、古代の祭祀場と推定されている。のどかな田園風景と大和高原に連なる、ゆるやかな丘陵地が周辺に広がり公園展望所からの眺望は、最高の奈良盆地を演出している。■鬼子母神社は櫟本高塚公園の北西に鎮座している。この神社は少し変わった造りの神社で、建物には板壁が存在しない風通し良い建物である。四隅の柱に屋根が乗る形で造られている。鎮座している神様は楕円形の石で表面にはなにも刻まれてない。遠くから見ると米粒の形に見える。 |
| ■櫟本かぼちゃ薬師堂 | |
| ■かぼちゃ薬師は、JR櫟本駅近くの楢(なら)町の集落の中に興願寺という寺があり、その前に薬師堂が建っている。江戸時代初期から春日厨子に安置されていた、木造薬師如来座像を本尊として祀り、如来の好物であるカボチャの初なりを供えると、癪(しゃく)の病や耳の病に治療効果があると言い伝えられている。 | |
| ■櫟本楢神社(ならじんじゃ・楢大明神社) | |
| 楢神社の趣のある銅鳥居 | 楢神社拝殿 |
 |
 |
 |
| 楢神社境内に有る鉄製の檻に囲まれた不思議な狛犬 | ||
| ■楢神社(楢大明神社)はカボチャ薬師堂より南西に位置し大変珍しい造りの鳥居がある。重圧感のある銅製で天皇陵の鳥居によく似た形である。日本書紀に登場する古い神社で祭神は五十狭芹彦命(イサセリヒコノミコト・吉備津彦命)で崇神天皇の御世に四道将軍(よつのみちのいくさのきみ)の1人である。五十狭芹彦命は鬼子母神を本地とすることから子どもの守護神であり神像はザクロの実を持っています。種子の多いザクロは多産のシンボルとされることから子授けの神として全国から多くの人が参拝に訪れました。また、参拝して子どもが授かると楢(なら)や奈良の字をもらって命名する習わしがあったという。境内には八代目・市川団十郎が奉納した実僧井(三枡井・みますい)の井筒があって、この井戸水は子供を授かる霊水といわれている。楢神社の■狛犬は檻の中に安置されていて、日が暮れると境内を散歩?・・するのを防いでいます。 |
| No04■六地蔵 | |
| ■六地蔵は森本寺山遺跡の中にある。昔は森本町、蔵之庄町、中之庄町・楢町・石川町(大和郡山市)の共同火葬場のお迎え地蔵といわれている。のどかな田園風景の中に優しくほほえむ地蔵の姿(写真右上)は大和路の写真集でも紹介されている。六地蔵は【地獄】【餓鬼】【畜生】【修羅】【人間】【天上】の迷界から人々を救うために六つの地蔵を立てるそうである。 |
| ■善福寺(ぜんふくじ) | |
| ■善福寺は浄土宗知恩院第十四世助阿上人を開基とする寺で文明九年(1477年)に創建された。本尊の木造阿弥陀如来坐像は国の重要文化財に指定されている。開山年代は平安藤原時代後期(1100年)【仏像拝観要予約】 問い=〒632-0002 奈良県天理市和爾町1217 TEL0743-65-5211 善福寺 善福寺から北方に■和邇坂下(わにさかもと)とよばれる伝承地があります。古事記・日本書紀に記されている和邇坂下・和邇坂とよぶ地名。日本書紀神武天皇に関する記述には「和邇坂下に巨勢祝(こせのはふり)という者あり」と記されている。神武天皇が大和を平定する際に逆賊として成敗した巨勢祝という土豪が、和邇坂下に拠点をもっていたことを示している。古事記の応神天皇に関する記述には和邇氏の娘、宮主矢河枝比売(やかはえひめ)との出会いが記載されている。【応神天皇の記述】近江国行幸の時、応神天皇は木幡村(山城国宇治郡)で美しい少女に出逢った。名を問うと、宮主矢河枝比売(やかわえひめ)と名乗った。天皇は「明日帰って来たら、お前の家を訪ねよう」と言った。比売が家に戻って父にこの話をすると、父はその人が天皇であると察知し、家を飾って饗宴の席を設けた。翌日、天皇は約束通り矢河比売の家を訪問した。比売が盃を献ると、天皇はそれを受け取る前にこの歌を詠んだ、という。その後、二人は結婚し、宇治若郎子をもうけた。和邇氏がもてなす宴会で披露した天皇の長歌の中に「・・・櫟井の和邇坂・・・」と記されている。櫟井は、現在の櫟本付近の事で和邇坂がこの地域まで含まれる地名であった。また崇神天皇に反旗した山代の武埴安彦を征伐する説話がある。古事記には「丸邇臣の祖、日子玖命を副えて遣わしし時、即ち丸邇坂にイワイベを据えて罷り往きき」とあり、和邇氏の祖人、彦国プクが武埴安彦の征伐に出陣する際に戦勝祈願を和邇坂行っていたそうである。 |
| No05■弘仁寺(こうじんじ) | |
| ■弘仁寺は高野山真言宗の寺院で伽藍は本堂・明星堂・山門・奥の院がある。山号は虚空蔵山。本尊は虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)で伊勢の浅熊、福島の柳津と共に日本三大虚空蔵尊1つである。山の辺の北道の中ほどの小高い山、虚空蔵山の山腹にある寺院。毎年四月十三日の十三詣りで有名。通称「高樋(たかひ)の虚空蔵さん」と呼ばれている。この寺の歴史は弘仁五年(814年)嵯峨天皇(サガテンノウ)の勅願により空海が創建したと伝えられている。空海が自ら彫った、虚空像菩薩像を本尊として安置したと伝えられる。また、大同二年(807年)に、この地に明星(隕石)が隕ちたことから、空海が神聖な土地として、寺を建立したとも伝えられている。空海とは別に遣隋使を務めた小野妹子の子孫、小野岑守(オノノミネモリ)の長子で小野篁(オノノタカムラ)を創建者とする説もある。弘仁寺は元亀三年(1572年)茶人としても有名な松永久秀の兵火により、伽藍の大部分が焼失したが、寛永六年(1629年)再建された。本堂は奈良県指定文化財指定である。また、国の重要文化財として木造明星菩薩立像・明星堂本尊(平安時代初期)【奈良国立博物館寄託】木造持国天増長天立像・木造広目天多聞天立像等、その他の文化財として虚空蔵菩薩像(木造)地蔵菩薩像等がある。 |
| ■黄金塚古墳(こがねつかこふん)黄金塚陵墓参考地 | |
| ■黄金塚古墳は大和最大の磚槨式石室(せんかくしきせきしつ)である。南北約26.5mの方墳。築造時期は古墳時代終末期。 丘陵の南斜面にあたるが、背後の丘陵と墳丘を区分するための空堀状の施設が残されている。埋葬施設は榛原石(原産地は宇陀市)を使った磚槨式の横穴式石室で特殊な形をしている。玄室は長さ約3m幅3.3m、高さ約2.6mあって、羨道は長さ約9.6m。これを三等分するように柱状に突出部分がある。この部分の幅は約1.3m、柱のない部分の幅は約1.6m高さ約2.6m。玄室(げんしつ・遺体を収める部屋)、羨道(せんどう・狭い通路)ともに壁面には漆喰が塗られていた。この古墳の東側では板石の石棺が出土されており、副葬品はなく鉄釘の様な物と約30才前後の女性の歯が残されていた。言い伝えでは天武天皇の子、舎人親王(トネリシンノウ)の墓ともいわれている。この古墳は宮内庁管理でのため中を見ることが出来ない。 |
| No06■帯解寺(おびとけでら) | |
| 帯解寺山門 | 帯解寺本堂 |
| ■帯解寺は華厳宗の古い寺院。本尊は地蔵菩薩であり、俗に帯解地蔵と呼ばれている。弘法大師の師である勤繰大徳の開基した。巖渕坊(いわぶちぼう)の一院で霊松山と称す。今から約千年前に第五十五代文徳天皇(モントクテンノウ)の染殿皇后(ソメドノコウゴウ・藤原明子)に子が生まれず、天皇は祖神春日明神のお告げにより、勅使をたて帯解子安地蔵菩薩に祈ったところ、惟仁親王(コレヒトシンノウ・清和天皇)が生まれた。文徳天皇は喜び天安二年(858年)春には伽藍を建立、寺号を改め無事帯が解けた寺ということで帯解寺と勅命した。帯解の名称はここから始まったそうである。以来、帯解寺は信仰をあつめ、江戸期には徳川三代将軍家光からも厚い信仰をうけた。二十世紀以降も美智子皇后・雅子皇太子妃をはじめ三笠宮・高円宮・秋篠宮などの皇族が帯解寺において安産祈願を行っている。安産祈願の寺として世に知られ、現在の山号も子安山である。 |
| No07■正暦寺(しょうりゃくじ) | |
| No08■霊元天皇皇女墓所 | |
| ■後水尾天皇皇女墓所 | |
| ■圓照寺宮墓は後水尾天皇皇女文智女王墓、後伏見天皇十九世皇孫女文秀女王墓、霊元天皇皇曾孫女文乗女王墓、霊元天皇皇女文喜女王墓、霊元天皇皇孫女文亨女王墓、霊元天皇皇女永応女王墓、後水尾天皇皇女文察女王墓、後西天皇皇女瑞光女王塔、中御門天皇皇女永皎女王塔など歴代円照寺、門跡の皇女の墓所である。 |
| ■五ッ塚古墳群 | |
| ■五ッ塚古墳群は圓照寺宮墓の前にある五基からなる古墳群。丘陵後背部を掘削し盛土した山寄せの古墳である。また、山側に周溝があると考えられている。五基の古墳は、北に向かってW字形に配置されており、五基の円墳からなる。古墳群として知られていたが、測量調査の結果、谷側に少し張り出す二基が方墳であるとされた。埋葬施設はすべて横穴式石室。墳丘は一号、三号、五号墳が円墳、築造は六世紀後半。二号、四号墳が方墳、築造は七世紀頃とされている。五基の古墳は全て南に開口する横穴式石室です。現在は全ての古墳羨道は埋めてあり中に入ることは出来ません(市指定文化財) |
| No09■圓照寺(えんしょうじ) | |
| 圓照寺の黒木門 | 圓照寺黒門手前の・・山の辺の道 |
| 圓照寺山門 | 圓照寺・右に茅葺の本堂(円通殿) |
| ■普門山圓照寺(円照寺)は山の辺の道沿いにある美しい尼寺である。参道を上がると黒木の門があり、格式の高さうかがえる。創建は寛永十七年(1640年)後水尾天皇の第1皇女である、文智女王(幼名、梅の宮)が二二才の時、仏頂国師を師として出家され、大通文智となり寛永十八年(641年)京都の修学院の地に草庵を結びました。明暦二年(1656年)天皇による修学院離宮の造営により移転を迫られた。継母である中宮東福門院(徳川秀忠の娘)の助力により、幕府から200石(後に300石に加増)金1,000両の寄進を得て、大和国添上郡八嶋の地に移り、八嶋御所と称した。寛文九年(1669年)現在の地に再度移転した。円照寺は斑鳩の中宮寺、奈良市佐保の法華寺と共に大和三門跡といわれている。茅葺の本堂は円通殿【茅葺(八嶋御所)・奈良県指定文化財】・圓照寺本尊の木造如意輪観音像、塑像後水尾天皇像などが安置されている。この寺の伽藍は本堂 書院【寝殿造・唐破風の玄関】 宸殿【京都御所紫宸殿の古材を利用】 奧御殿 葉庵帰である。臨済宗妙心寺派に属する門跡寺院で、代々皇室係の方が門跡になっている。平成七年四月十二日に八十才で亡くなられた、第十代山本静山(じょうざん)門跡は昭和天皇の妹君、糸子内親王といわれている。華道では「山村御流(ごりゅう)」の家元でもあり、別名は山村御殿とも呼ばれている。小説では三島由紀夫の『豊饒の海』に再三登場する「月修寺」は圓照寺をモデルに描かれたといわれている。また、大和国帯解山村廃寺出土品【重要文化財】を奈良国立博物館寄託している。※円照寺は非公開のため拝観できません。 |
| No10■崇道天皇八嶋陵 | |
| 崇道天皇八嶋陵逢拝所 | 崇道天皇陵手前、道路中央の古墳の石室部 |
| ■崇道天皇八嶋陵(スドウテンノウヤシマノミササギ)は早良親王(サワラシンノウ)の墓とされている。早良親王は、奈良時代末期の皇族で光仁天皇(コウニンテンノウ)の皇子。母は高野新笠(タカノノニイガサ)。平安京造営や平氏の祖として有名な桓武天皇(カンムテンノウ)・能登内親王(ノトナイシンノウ)の同母弟。早良親王は実の母方が下級貴族であるため、皇位継承は望んでいない皇子であった。天平宝字六年(761年)に出家し、東大寺羂索院や大安寺東院に住み、親王禅師と呼ばれていたが、天応元年(781年)兄である桓武天皇の即位と同時に、光仁天皇の勧めにより皇位継承者となった。その頃、藤原種継(フジワラノタネツグ)が中心に行っていた長岡京造営の目的の1つに、東大寺・大安寺などの南都寺院の影響力を潰す考えが浮上し、藤原種継暗殺事件が起こった。事件後、東大寺華厳別供縁起に東大寺の開山した僧侶である良弁が、死の間際に東大寺にいた親王禅師(早良親王)に後の事を託したそうである。東大寺権別当実忠二十九ヶ条に東大寺が親王の還俗後も、寺の大事に関しては必ず親王に相談後に行っていたと伝えられている。この事から南都寺院と関係深い、早良親王が遷都の阻止するために、藤原種継暗殺に関与した疑いをかけられたといわれている。その後、早良親王は藤原種継暗殺事件に関与した罪を受け、淡路島に流される途中の河内国高瀬橋付近の船上で憤死(ふんし・身の潔白を証明するための死)したと伝えられる。その後、桓武天皇の長男安殿親王(アテシンノウ・平城天皇)の発病や桓武天皇妃藤原乙牟漏(フジワラノオトムロ)の病死などが、相次ぎ桓武天皇は早良親王の祟りであるとして淡路国に埋葬されていた、早良親王の墓を延暦十九年(800年)八月に淡路国から大和国添上郡八島に移葬した。祟りを恐れ、親王の怨霊に対し幾度も鎮魂の儀式を行った。歴代天皇の中に崇道天皇の名は記されていないが桓武天皇が同年に怨霊鎮魂のため、崇道天皇という諡号を与えたそうである。陵の近辺には早良親王を祀る嶋田神社があり、北方向の奈良市紀寺町には崇道天皇社・御霊神社など祭神として祀られている。陵前の道を分断するように中央に■古墳の石室部分といわれる巨石が置かれている。道の中央に置かれていて危険であるが、この巨石を他の場所に移動すれば祟りがあると言い伝えられている。 |
| ■嶋田神社 | |
| ■嶋田神社は崇道天皇八嶋陵から東の丘陵に位置する神社。この本殿は春日大社から移した社である。春日大社古事録によると、享保十二年(1727年)春日大社が第四五次式年遷宮による造営のとき、旧本殿のうち第二殿を八嶋村へ譲渡したとある。しかし、擬宝珠(ぎぼうし)の銘には更に古く記されている。移築当時に近い形状を残し、貴重な社である。嶋田神社本殿一棟は奈良市指定文化財(昭和五十七年三月)指定されています祭神は神武天皇の皇子てある神八井耳命(カムヤイミミノミコト)・早良親王(サワラシンノウ・崇道天皇)を祀っている。 |
| ■崇道天皇社 | |
| ■崇道天皇社は平城天皇大同元年(806年)の創立。早良太子(崇道天皇)の霊を鎮めるために祀られる。 |
| ■崇道天王社 | |
| ■崇道天皇神社 | |
| No11■奈良県護国神社(ならけんごこくじんじゃ) | |
| ■奈良県護国神社は明治維新から第二次世界大戦までの国難に殉じた、奈良県出身の陸海軍戦没者29,110柱の英霊を祀ている。昭和十四年(1939年)六月に奈良県知事を会長として護国神社建設奉賛会が組織され、昭和十五年十月に創立を許可された。同年に造営を開始し、昭和十七年(1942年)に竣工し、内務大臣指定護国神社となった。この神社は日本国に命を捧げた殉職者などを、英霊として祀る神社である。護国神社とは明治時代に日本の各県に建立された、招魂社が昭和十四年(1939年)の内務省令によって一斉に改称したもである。各府県につき1社を府県社に相当する内務大臣指定護国神社(指定護国神社)とし、それ以外を村社に相当する指定外護国神社とした。敗戦後は護国神社は軍国主義施設と見なされ、神社存続を図るために名称から護国神社の文字を外して高円神社(たかまどじんしゃ)とよばれていた。サンフランシスコ平和条約を締結し日本が独立を回復すると元の社名に戻したそうである。各県の神社としては珍しく、青森縣護国神社だけは改称せず「護国神社」を守り通したそうである。戦後いくつかの指定護国神社は神社本庁の別表神社となり、護国神社の祭神は分祀されたのではなく、独自で招魂し祭祀を執り行っているため、公式には靖國神社とは本社分社の関係はないとされている。共に英霊を祀る靖國神社と護国神社と交流があるそうである。主要な護国神社五十二社で組織する、全國護國神社會(旧浦安会)は靖國神社と連携し英霊顕彰の為の様々な活動を行っている。昭和三十五年(1960年)全国の護国神社五十二社に対して、天皇・皇后より幣帛が下賜されて以降、終戦から数えて10年毎に幣帛の下賜が続けられている。靖國神社も護国神社と同様に戦死者を英霊として祀る神社であり、招魂社を改称したものであるが、太平洋戦争当時まで日本人とされていた朝鮮・台湾の人も含め、日本全国どこの出身であっても祀られる点が異なっている。この神社は山の辺の道とは関係がないものの、日本のために戦い、亡くなられた人たちを祀った神社である。 |
| No12■白毫寺(びゃくごうじ) | |
| 白毫寺山門 | 白毫寺本堂 |
| 静かな雰囲気の白毫寺境内 | 白毫寺境内展望所からの奈良盆地 |
| ■白毫寺は真言律宗の寺院である。高円山の山麓に建立されており、境内からの奈良盆地の展望は素晴らしいところで有名である。霊亀元年(715年)天智天皇の第七皇子である志貴皇子の没後、天皇の勅願によって皇子の山荘跡を寺としたのが始まりと伝えられている。また、高円山付近に存在した石淵寺(いわぶちでら)の一院でるともいわれている。石淵寺は空海の剃髪の師であった勤操(ごんそう)が建てたとされる寺院である。鎌倉時代になって西大寺の叡尊によって再興され、弘長元年(1261年)叡尊(えいぞん)の弟子である道照(どうしょう)が中国から宋版一切経の摺本を持ち帰り、翌年から毎年、一切経会(いつさいきょうかい)を行い、別名で一切経寺とも呼ばれて庶民信仰の場として繁栄したが室町時代には兵火により、建物が焼失し衰退した。その後、江戸時代の寛永年間(1630年)頃に興福寺の学僧空慶上人により、復興された。現在も毎年八月八日には「一切経会」が行われている。また、重要文化財では白毫寺の本尊である、木造阿弥陀如来坐像は檜材を用いた寄木造りの仏像で、平安時代末期から鎌倉時代頃の作。木造菩薩坐像(伝文殊菩薩)多宝塔の本尊とされる白毫寺最古の仏像は平安初期の作。木造地蔵菩薩立像は地蔵菩薩像の秀作で鎌倉時代後期の作であり彩色も鮮やかに残っている。木造興正菩薩坐像は白毫寺を中興した興正菩薩・叡尊の肖像彫刻で叡尊晩年の姿像。木造閻魔王坐像は閻魔堂の本尊といわれる鎌倉時代の作。木造太山王坐像は閻魔王と同じく冥界の十王の一人、鎌倉時代の運慶の孫、康円の作。木造司命半跏像・司録半跏像は閻魔王の眷属、康円一派の作。本堂は奈良市指定文化財である。この寺の境内には奈良三名椿の一つである、樹齢四百年の五色椿(寛永年間に興福寺の塔頭、喜多院から移植・奈良県指定天然記念物)があり、東大寺開山堂の糊こぼし、伝香寺の散り椿とともに有名である。境内には他に御影堂・宝蔵・石庭・椿園・万葉歌碑などがもある。 |
| No13■新薬師寺(しんやくしじ) | |
| 新薬師寺山門と本堂 | |
| ■新薬師寺は華厳宗の寺院。本尊は薬師如来、創立者は光明皇后(コウミョウコウゴウ)または、聖武天皇(ショウムテンノウ)といわれている。奈良時代には南都十大寺の1つに数えられ寺地は約440m四方を有していた。現在の奈良教育大学のキャンパスあたりまでが、新薬師寺の境内地であった。東大寺要録によれば、光明皇后が夫である聖武天皇の病気平癒を祈願して、天平十九年(747年)に建立し、七仏薬師像を安置したとされている。この時の聖武天皇の病気は大病ではないと、天平十七年(745年)の続日本紀に記されている。そのことから平癒のために発願されたといわれている。また、新薬師寺の本尊である木造薬師如来坐像は高さ約2mで構造は一木造であり眉・瞳・髭などに墨、唇に朱を使い他は彩色や金箔を施さない像である。一般の仏像より眼が大きく造られていることから、聖武天皇が光明皇后の眼病平癒を祈願して天平十七年(745年)に建立したともいわれている。寺名の「新」は「霊験あらたかな」の意味のようである。また、新薬師寺の東方には春日山があり、山の中に光明皇后の発願による香山堂(こうぜんどう・香山薬師寺)と呼ばれる、寺院が存在したことが記録や発掘調査から知られている。香山堂が新薬師寺の前身であり、後に新薬師寺と合併したともいわれる。香山堂は1966年の発掘調査で、佐保川の水源地付近の尾根上に寺院跡が確認され、東大寺大仏造立時期の瓦が出土している。天平勝宝八年(756年)の東大寺山堺四至図(とうだいじさんかいしいしず)【正倉院宝物】に新薬師寺と香山堂の両方が記されていて、当時は両寺院が存在していたことがうかがえる。創建時の新薬師寺は金堂・東西両塔などの七堂伽藍が建ち並ぶ大寺院であったが、次第に衰退し続日本紀によれば宝亀十一年(780年)の落雷で西塔が焼失し、その周りの建物も焼失したそうである。日本紀略・東大寺要録によれば応和二年(962年)台風で金堂以下の主要堂宇が倒壊し復興したが、当時の規模に出来なかったそうである。現在の本堂(入母屋造・本瓦葺)【国宝】は奈良時代建築ではあるが、他の堂を転用したものらしい。本尊の薬師如来像も八世紀末頃の制作と見られている。治承四年(1180年)の平重衡の兵火で東大寺・興福寺は主要伽藍を焼失したが、新薬師寺は焼け残り鎌倉時代には華厳宗中興の祖である明恵(みょうえ)が一時入寺して、復興に努めた。現存する本堂以外の主要建物は鎌倉時代のものである。 |
| No14■春日大社(かすがたいしゃ) | |
| 珍しい神鹿の手水社 | 春日大社南門【重文】 |
| 春日大社南回廊に並ぶ石灯籠 | 春日大社南回廊 |
| 春日大社南門【重文】と石灯籠 | 舞殿から見る中門・御廊【重文】 |
| ■春日大社は奈良公園内にある神社。式内社(名神大社)二十二社の一社で旧社格は官幣大社であり、全国春日神社の総本社でもある。歴史は奈良・平城京に遷都された和銅三年(710年)藤原不比等(フジワラノフヒト)が藤原氏の氏神である、鹿島神(武甕槌命・タケノミカヅチノミコト)を春日の御蓋山に遷して祀り、春日神と称したのに始まる。社伝では神護景雲二年(768年)に藤原永手(フジワラノナガテ)が鹿島の武甕槌命・香取の経津主命(フツヌシ)と枚岡神社に祀られていた天児屋根命(アメノコヤネノミコト)妻の天美津玉照比売命(アメノミツタマテルヒメノミコト・比売神)を併せて、御蓋山の麓の四殿の社殿を造営したのをもって、創祀としている。嘉承三年(850年)に武甕槌命・経津主命。天慶三年(940年)には天児屋根命が最高位である、正一位の神階を授かったそうである。武甕槌命が白鹿に乗ってやってきたと、されることから鹿が神使とされている。延喜式神名帳には大和国添上郡春日祭神四座と記され、名神大社に列して月次・新嘗の幣帛に預ると記されている。本殿は春日造の本殿が四殿並んで建っており、第一殿に武甕槌命、第二殿に経津主命、第三殿に天児屋根命、第四殿に比売神が祀られている。明治四年に春日神社に改称し官幣大社に本列し、昭和二一年十二月に、現在の春日大社に改称した。春日大社はは広大な境内に多数の摂社・末社があり、本殿の東側には比売神の御子神として、天押雲根命を祀る摂社若宮神社・若宮神社、夫婦大国社を始めとする、本殿東側の十二社は福の神十二社めぐり、として古来より人気がある。本殿廻廊の西南隅には榎本神社(式内小社)があって祭神は元々この地で祀られていた地主神であるとされている。現在の祭神は猿田彦大神であるが、中世までは巨勢姫明神とされていた。この神社の重要無形民俗文化財で春日若宮おん祭の神事芸能(春日若宮おん祭保存会)や選択無形民俗文化財で春日若宮おん祭の芸能(春日古楽保存会)等がある。その他に世界遺産・文化遺産で古都奈良の文化財、国指定史跡の春日大社境内、天然記念物の春日神社境内ナギ樹林、■特別天然記念物の春日山原始林となっている。春日大社の一鳥居は気比神宮、厳島神社の大鳥居に並ぶ日本三大鳥居の一つでもある。また、近年の境内の発掘調査によって神護景雲以前より、この地で祭祀が行われていた可能性がある。 |
| ■天然記念物の春日山原始林 | |
| No15■氷室神社(ひむろじんじゃ) | |
| ■氷室神社は春日野に元明天皇和銅三年(710年)に吉城川の上流で■月日の磐に氷池や氷室を造り、呼び名を吉城川氷室・春日氷室・水谷氷室という。稲作に重要な夏の天候を呪う祭紀を行ったのが始まりとされている。冬期に凍らせた氷を氷室(土を掘り茅萩を敷き、その中に氷を入れて上に草等で覆うと氷が日持ちする)に貯え、翌年夏期に平城京へ献上する慣わしで、献氷祭が行われていた。日本書紀の仁徳天皇六二年の条に、皇子が闘鶏(都祁)稲置大山主命(ツゲノイナギオオヤマヌシノミコト)から、氷室のことを知り皇子は氷を御所に献上したそうである。この氷を昔の酒(ドブロク)に入れオンザロックで飲まれていた可能性がある。氷室神社は平安遷都後、貞観二年(860年)現在地に移った。社殿の建立は健保五年(1217年)とされている。この神社の祀主は闘鶏稲置大山主命・大鷦鷯命(オオサザキノミコト・仁徳天皇)・額田大仲彦命(ヌカタノオオナカツヒコノミコト・仁徳天皇の弟)である。また楼門(棟札に江戸時代初期の寛永十九年(1642年)に修理と記されている)・東西御廊は奈良県文化財に指定されている。本殿は三間社流造・桧皮葺であり、江戸時代末期の造営で県指定文化財になっている。神社の宝物は木造舞楽面・陵王面一面(鎌倉時代)重要文化財などがある。毎年五月一日には、コイ・タイを封じ込めた高さ約1mの氷柱が神前に供えられ、献氷祭を行っている。この神社の枝垂れ桜は奈良市内で一番最初(三月下旬)に咲くのが有名である。 |
| 月日の磐を取り巻く原始林 | 清流の淵にある月日の磐 |
| No16■若草山(三笠山)・鶯陵 | |
| 若草山 | 山が重なるように見える若草山 |
| 若草山頂上から望む奈良 | 若草山頂上の鶯陵古墳跡 |
| ■若草山(わかくさやま)は奈良公園の東端に位置する。標高342m面積3.3haの山であり、山が三つ折り重なっているため三笠山(みかさやま)とよばれている。年行事である、1月に行われる山焼きは1760年に東大寺と興福寺による領地争いが発端といわれている。1935年、この山名に因んで三笠宮が創設される際に、同じ名前では恐れ多いとして、山焼きに因んで若草山に改称したそうである。また、若草山の山頂から見る奈良の夜景は生駒山のような華々しい光量はないもの、古都奈良の風情豊かな見晴らしがあり、新日本三大夜景のひとつに認定されている。■日露戦争での日本海海戦の旗艦、戦艦「三笠」はこの山の名に因んで命名されたそうである。■若草山山頂には枕草子にも登場する仁徳天皇(ニントクテンノウ)の皇后、磐之姫命(イワノヒコノミコト)の墓といわれている、全長103mの前方後円墳。現在は後円部に「鶯陵」の石碑が立っている。築造は四世紀末で標高300m以上の山頂にある古墳としては、我が国で最大級である。また甘党に好まれる「関西のどら焼き」は形が三笠山に似ていることから三笠まんじゅう、三笠焼きとよばれている。近年は特大の「三笠焼き」を奈良名物として販売するお店もある。余談であるが、阿倍仲麻呂の和歌「あまのはらふりさけみれば春日なる三笠の山に出でし月かも」の三笠の山は若草山の南隣の春日山をいう。春日山は別名、御蓋山(みかさやま)とよばれ太古の昔から霊山であった。山頂には春日大社第一の祭神武甕槌命(タケミカヅチノミコト)が768年に白鹿に乗り、天降ったとされている神跡があり、本宮神社(春日大社)として祀られている。 ■若草山開山予定日・・春期=3月17日〜6月17日・秋期=9月8日〜11月25日 ■毎年多少開山日が異なることがある。【入山料】大人150円小人80円(午前九時〜午後五時) |
| ■奈良奥山ドライブウェイ | |
| 奈良奥山ドライブウェイにある東大寺旧境内跡・静かに鎮座する有名な三体地蔵菩薩 | |
| No17■二月堂・三月堂 | |
 |
 |
| ■二月堂(2005年12月、国宝に指定)は斜面に建てられた、懸崖造りの寺院である。修二会(しゅにえ)の創始者である実忠和尚により、天平勝宝四年(752年)の創建とされている。寛文七年(1667年)火災により全焼したが二年後に焼失前の姿に再建され、現在まで存在している。毎年三月一日〜三月十四日に行われる、千二百五十年以上の歴史を持つ、修二会(別名・お水取り)が行われている。名前の由来は旧暦の二月に修二会が行われてきたことから、二月堂の名がついたそうである。修二会とは11名の僧侶(練行衆)が二月堂の本尊の大観音(おおがんのん)小観音(こがんのん)と呼ばれる、二体の十一面観音(絶対秘仏)に国家安泰と人々の豊楽を祈るそうである。六時の行法ともばれる厳しい行でもある。初夜(19時)の行のため、二月堂へ上がる練行衆の足元を照らす松明(おたいまつ)の火の粉を浴びると無病息災といわれ、毎年多くの人々がお参りしている。中でも三月十二日のお水取り行事の籠松明は壮観である。二月堂の舞台からは大仏殿や奈良市内を一望することができる人気の場所でもある。堂下には『お水取り』の香水を汲み上げる■閼伽井(あかい)屋がある。■三月堂は法華堂(国宝)ともよばれている。寺内最古の天平建築の一ッと数えられ、天平仏の宝庫としても知られている。東大寺の前身である、金鐘寺(こんしゅじ)の羂索堂(けんさくどう)として建立されたもので、寄棟造りの本堂と入母屋造りの札堂からなるが、札堂は鎌倉時代に付設されたものである。時代の異なる二ッの棟をつなげて一棟のよう見せており、美しい調和がとられた日本の名建築といわれている。記録では天平十五年(743年)には完成していた。堂々の天平仏の宝庫として、天平彫刻の傑作が多く安置されている。■乾漆不空羂索観音立像【(国宝)奈良時代】■塑造日光・月光(がっこう)菩薩立像【(国宝)奈良時代】■乾漆梵天・帝釈天立像【(国宝)奈良時代】■乾漆金剛力士立像【(国宝)奈良時代】■乾漆四天王立像(国宝)■塑造執金剛神立像(国宝)■塑造吉祥天・弁才天立像【(重文)奈良時代】■木造不動明王二童子像【(重文)南北朝時代】■木造地蔵菩薩坐像【(重文)鎌倉時代】正に天平仏の宝の宝庫である。また特に女性人気の、しなやかな手を持つ月光菩薩は素晴らしい出来映えの仏像である。入堂料大人400円 入堂時間 8時〜17時 |
| ■三月堂・閼伽井屋(あかいや) | |
| 風格有る三月堂【上写真】・お水取りで有名な閼伽井屋【下写真】 | |
| No18■東大寺(とうだいじ) | |
 |
 |
| ■東大寺は華厳宗大本山の仏教寺院で金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)という。奈良時代(八世紀)に聖武天皇(ショウムテンノウ)が国力を尽くし、建立した寺である。奈良の大仏として世に知られる■盧舎那仏(るしゃなぶつ)を本尊とし、開山したのは良弁僧正(ロウベンソウジョウ)である。現存する大仏は台座などの一部に、当初の部分を残すだけである。また大仏殿は江戸時代十八世紀初頭の再建であり創建当時の堂に比べ間口が三分の二に縮小されている。奈良時代には中心堂宇の大仏殿(金堂)のほか東西二つの高さ約100mの七重塔を含む、大伽藍があったが中世以降に二度の兵火をあびており、多くの建物を焼失しましたが大仏さんの寺として、古代から現代に至るまで官・民差別なく広い信仰を集め日本の文化に大きな影響力をもつ寺院であった。聖武天皇は奈良時代中期の天皇で文武天皇の皇子である。藤原不比等の娘である光明子(コウミョウシ・光明皇后)を后とした。即位してまもなく、貴族どうしの勢力争いや疫病の流行など、不安定な時代がつづいたために都を各地に転々と遷し745年に平城京に遷つた。天皇は積極的に唐(中国)の文化をとり入れる一方、仏教を深く信仰して全国に国分寺と国分尼寺をつくり、都にも国分寺を建立して大仏を祀った。天皇の治世を中心に、仏教中心の天平文化が栄えた。聖武天皇は当時の日本の六十余か国に建立させた国分寺の本山にあたる総国分寺(東大寺)と位置づけした。東大寺の起源は大仏造立よりやや古く、八世紀前半には大仏殿の東方、若草山麓に前身寺院が建立されていた。東大寺の記録である『東大寺要録』によれば天平五年(733年)若草山麓に創建された金鐘寺(こんしゅじ)が東大寺の起源であるとされている。また『続日本紀』によれば神亀五年(728年)第四十五代天皇である、聖武天皇と光明皇后が年若く亡くなった皇子の菩提のために若草山麓に山房を設けて九人の僧侶を住まわせた。これが金鐘寺の前身といわれている。金鐘寺には八世紀半ばには羂索堂・千手堂が存在したことが記録から知られ、羂索堂は現在の法華堂(三月堂)といわれている。天平十三年(741年)には国分寺建立の詔(みことのり)が発せられ、翌天平十四年(742年)金鐘寺は大和国名の国分寺と定められて、金鍾寺の寺名は金光明寺と改められた。東大寺の寺名は大仏の鋳造が始まった天平十九年(747年)であり、この頃から東大寺と呼ばれるようになった。聖武天皇が大仏造立の詔(みことのり)を発したのはそれより前の天平十五年(743年)である。都は一時期、恭仁京(くにのみや)に移されていたが天皇は恭仁京の北東に位置する、紫香楽宮(しがらきのみや)にあり大仏造立をこの地で始められた。聖武天皇は短期間に遷都を繰り返したが、二年後の天平十七年(745年)都が平城京に遷るとともに、大仏造立も東大寺の地で始めることになるが大事業を推進するには民衆の支持が必要であった。その頃、朝廷から弾圧されていた行基(ギョウキ)を大僧正として迎え協力を得た。行基は河内国大鳥郡の生まれ。681年に出家し官大寺で法相宗などの教学を学び集団を形成して関西地方を中心に貧民救済や治水 架橋などの社会事業に活動した。704年に生家を家原寺とし居住した。民衆を煽動する人物であり、寺外の活動が僧尼令に違反するとして養老元年(717年)四月二十三日弾圧を受けた。行基の指導による墾田開発や社会事業の進展や地方豪族や民衆らを中心とした教団の拡大を防げない行基の活動を政府が恐れていた。また行基の活動は反政府的な意図がないことから、天平三年(731年)禁圧を緩め、翌年河内の狭山下池の築造に行基の土木技術や農民動員の力量を利用した。天平十三年(741年)三月に聖武天皇が恭仁京郊外の泉橋院で行基と会見し、同十五年東大寺の大仏造造営の勧進に起用されている。勧進の効果は大きく天平十七年(745年)に朝廷より日本最初の大僧正の位を贈られた。行基の活動と国家からの弾圧に関しては、奈良時代に僧尼令違反で処分されたのは行基のみと言われている。同時代の中国で席捲していた、三階教教団活動と唐朝の弾圧との関連や影響関係が指摘されている。三世一身法が施行されると、灌漑事業や東大寺大仏造立に関わっている。大仏造営中の天平二十一年(749年)二月二日、菅原寺で81才で亡くなり、生駒市の竹林寺に葬られている。朝廷より菩薩の称号が与えられ、行基菩薩とも言われている。大仏の鋳造が幾多の難工事の末、終了し天竺(インド)出身の僧侶で菩提僊那(ボダイセンナ)を導師として、天平勝宝四年(752年)大仏開眼が行われ、その後に天平宝字二年(758年)大仏殿の建設工事が始められた。東大寺では大仏創建に力のあった良弁、聖武天皇、行基、菩提僊那を四聖(ししょう)とよばれている。東大寺は大仏造立 大仏殿建立のような大規模建設工事は国費を浪費させ日本の財政事情が悪化した。聖武天皇の思惑とは程遠い事実がうかがえる。貴族、寺院が栄える一方、農民層の負担が激増し平城京内では浮浪者や餓死者が後を絶たず、租庸調の税制も崩壊寸前になる地方も出るなど、律令政治の大きな誤算が浮き彫りになった。天平勝宝八年(756年)五月二日、聖武天皇が亡くなり。同年七月に橘奈良麻呂(タチバナノナラマロ)の乱が起こった。同年七月四日に逮捕された橘奈良麻呂は藤原永手の聴取に対し「東大寺などを造営し人民が辛苦している。政治が無道だから反乱を企てた」と謀反を白状した。永手は「東大寺の建立が始まったのは奈良麻呂の父(橘諸兄)の時代である。とやかく言われる筋合いは無い。それ以前に奈良麻呂とは何の因果もないはず」と反論した。奈良麻呂は返答に詰まったと言われている。奈良時代の東大寺伽藍は南大門・中門・金堂(大仏殿)講堂が南北方向に、一直線に並び講堂の北には東西に「コ」の字形に僧房、僧房の東に食堂(じきどう)があり南大門・中門間の左右には東西2基の高さ約100mの七重塔が回廊に囲まれて建っていた。天平十七年(745年)の起工から伽藍が一通り完成するまでには、四十年近い時間を要していた。中世以降の東大寺は興福寺と同じく、治承四年十二月二十八日(1181年1月15日)の平重衡の兵火で壊滅的な打撃(南都焼討)を受け、大仏殿や多くの堂塔を失った。その後、大仏や諸堂の再興に俊乗坊重源(しゅんじょうぼうちょうげん)が起用され重源の精力的な活動により、文治元年(1185年)には後白河法皇臨席のもと、大仏開眼法要が行われ建久元年(1190年)には再建大仏殿が完成、源頼朝らの列席のもと落慶法要が営まれた。戦国時代の永禄十年十月十日(1567年11月10日)三好・松永の戦いの兵火により大仏殿を含む東大寺の主要堂塔はまたも焼失した。大仏の修理は元禄四年(1691年)に完成し、再建大仏殿は公慶上人の尽力で宝永六年(1709年)に完成した。この三代目の大仏殿(現存)の高さは天平時代とほぼ同じであるが、間口は天平創建時の三分の二に縮小されており、徳川幕府の援助をもってしても、当初の規模を再現することは不可能であった。また講堂、食堂、東西の七重塔など近世以降は再建されることはなく、現在は各建物跡に礎石が残されているだけである。東大寺は1998年に古都奈良の文化財の一部としてユネスコより世界遺産に登録されました。 |
| No19■興福寺(こうふくじ)・奈良公園 | |
| 南円堂 | 三重塔 |
| ■興福寺(こうふくじ)は南都六宗の一っである。法相宗大本山寺院では南都七大寺の一ッに数えられている。藤原氏の祖の藤原鎌足と、その子息である藤原不比等ゆかりの寺院であり、藤原氏の氏寺でもる。古代〜中世にかけて強大な勢力を誇っていた。南円堂は西国三十三箇所第九番札所である。古都奈良の文化財の一部として世界遺産に登録されている。創建は藤原氏の祖である藤原鎌足夫人の鏡王女(かがみのおおきみ)が夫の病気平癒を願い、鎌足発願の釈迦三尊像を本尊として、天智天皇八年(669年)・山背国(山城国)・山階(京都市山科区)に創建した、山階寺(やましなでら)が興福寺の起源といわれている。壬申の乱が勃発した、天武天皇元年(672年)に山階寺は藤原京に移り、地名(高市郡厩坂)をとって、厩坂寺(うまやさかでら)と称したそうである。和銅三年(710年)の平城遷都に際し、鎌足の子息である藤原不比等は厩坂寺を平城京左京の現在地に移転し興福寺と名付け、この710年が実質的な興福寺の創建年といえるそうである。中金堂の建築は平城遷都後まもなく開始されたといわれている。その後も天皇や皇后、また藤原家によって堂塔が建てられ、整備が進められれていて、不比等が没した養老四年(720年)には造興福寺仏殿司という役所が設けられ、藤原氏の私寺である興福寺の造営は国家の手で進められるようになった。興福寺は奈良時代には四大寺、平安時代には七大寺の一ッに数えられ、特に摂関家藤原北家との関係深く、そのため手厚く保護されていた。平安時代には春日社の実権をもち、大和国一国の荘園の大半を領して事実上の同国の国主となり、その勢力の強大さは、比叡山延暦寺とともに南都北嶺(なんとほくれい)と称された。寺の周辺には院と称する数多くの付属寺院が建てられ、最盛期には100院以上を数えるほどであったが、中でも天禄元年(970年)定昭の創立した一乗院と寛治元年(1087年)隆禅の創立した大乗院は皇族・摂関家の子弟が入寺する門跡寺院として栄えた。鎌倉・室町時代には幕府は大和国に守護を置かず、興福寺がその任に当たる。文禄四年(1595年)の検地では、春日社興福寺合体の知行として二万一千余石とされたそうである。また興福寺は創建以来たびたび火災に見まわれたが、その都度再建を繰り返してきた。中でも治承四年(1180年)、源平の争いの最中、平重衡の兵火による被害は甚大であった(南都焼討)。この時は東大寺とともに大半の伽藍が焼失した。その後、興福寺再興に奔走したのは回禄直後に別当職に就いた信円と解脱上人貞慶であった。現存の興福寺の建物はすべてこの火災以後のものである。仏像をはじめとする、寺宝類も多数が焼失したため、現存するものは、この火災以後の鎌倉復興期に制作されたものが多く興福寺を拠点とした、運慶ら慶派仏師の手になる仏像もこの時期に数多く作られている。江戸時代になり享保二年(1717年)の火災時は、時代背景の変化もあって大規模な復興はされず、この時焼けた西金堂、講堂、南大門などは再建されなかった。また興福寺の伽藍は南円堂、中金堂(ちゅうこんどう)、東金堂(とうこんどう)、西金堂(さいこんどう)の三ッの金堂があり、それぞれに多くの仏像が安置されていた。寺の中心部には南から北に南大門、中門、中金堂、講堂が一直線に並び、境内東側には南から五重塔、東金堂、食堂(じきどう)が、境内西側には南から南円堂、西金堂、北円堂が建っていた。この他、境内南西隅の一段低い土地に三重塔が、境内南東部には大湯屋がそれぞれ建てられた。これらの堂宇は、創建以来たびたび火災に見舞われ、焼失と再建を繰り返してきた。明治期以降、興福寺の境内は奈良公園の一部と化し、寺域を区切っていた塀や南大門もなくなり、天平時代の整然とした伽藍配置を想像することは出来ない。■中金堂は藤原鎌足発願の釈迦三尊像を安置するための、寺の中心的な堂として和銅三年(710年)の平城京遷都直後に造営が始められたと推定されている。後、東・西金堂が建てられてからは中金堂と呼ばれています。創建以来たびたび焼失と再建を繰り返したが江戸時代の享保二年(1717年)の火災による焼失後は一世紀以上再建されず文政二年(1819年)篤志家の寄付により、ようやく再建された。この文政再建の堂は仮堂で規模も従前の堂より一回り小さく造られていたが興福寺国宝館の開館(1959年)までは、高さ5.2mの千手観音像をはじめ、多くの仏像を堂内に安置していた。■東金堂(国宝)は神亀三年(726年)、聖武天皇が伯母にあたる元正太上天皇の病気平癒を祈願し薬師三尊を安置する堂として創建した。治承四年(1180年)の兵火による焼失後、文治三年(1187年)、興福寺の僧兵は飛鳥の山田寺(現・奈良県桜井市)講堂本尊の薬師三尊像を強奪しており東金堂本尊に据えた。東金堂はその後応永十八年(1411年)に五重塔とともに焼け、現在の建物は応永二二年(1415年)の再建である。室町時代の建築であるが規模、形式ともに天平時代の堂に準じているそうである。■五重塔(国宝)は天平二年(730年)、光明皇后の発願で創建された。現存の塔は応永三三年(1426年)頃の再建である。高さ50.8mで木造塔としては東寺五重塔に次ぎ、日本で二番目の高さである。■北円堂(国宝)は養老五年(721年)、藤原不比等の一周忌に際し、元明上皇、元正天皇の両女帝が長屋王に命じて創建させたものである。現在の建物は承元二年(1208年)頃の再建で、興福寺に現存している建物の中では最も古い建物といえる。法隆寺夢殿と同様、平面が八角形の「八角円堂」である。■南円堂(重文)は弘仁四年(813年)、藤原北家の藤原冬嗣が父・内麻呂追善のため創建した。現在の建物は寛政元年(1789年)の再建であり。創建時の本尊は、もと興福寺講堂に安置されていた不空羂索観音像であった。この像は天平十八年(748年)、その前年に没した藤原房前の追善のため、夫人の牟漏女王、子息の藤原真楯らが造立したものである。堂は西国三十三箇所の九番札所として参詣人が絶えないが残念なことに、堂の扉は常時閉ざされており、開扉は10月17日の大般若経転読会という行事の日のみである。■三重塔は康治二年(1143年)、崇徳天皇の中宮・皇嘉門院により創建された。現在の塔は治承四年(1180年)の大火後まもなく再建された鎌倉建築である。■西金堂跡は天平六年(734年)光明皇后が母・橘三千代の一周忌に際し、釈迦三尊を安置する堂として創建した。江戸時代の享保二年(1717年)の火災による焼失後は現在まで再建されていない。■大湯屋は五重塔の東方に建つ。五重塔と同じく応永三三年(1426年)の再建である。■菩提院大御堂は五重塔の南、三条通りを渡った場所に位置する興福寺の子院である。現在の堂は天正八年(1580年)の再建で本尊阿弥陀如来坐像(重文)などを安置している。■本坊は境内東方に位置しているが一般に公開されていない。 |
 |
| ■奈良公園は奈良県奈良市の若草山麓に広がる都市公園であり国の名勝です。太政官布達により明治十三年(1880年)二月十四日開園。公園の大部分が国有地で奈良県が無償で借用し管理しています。都市公園としての正式名称は「奈良県立都市公園 奈良公園」とよばれ総面積は502ha。周辺の興福寺・東大寺・春日大社・奈良国立博物館なども含めると総面積はおよそ660ha(東西約4km・南北約2km)に及びます。通常はこの周辺社寺を含めたエリアを奈良公園とよぶことが多い。公園内には多くの国宝指定・世界遺産登録物件が点在し年間を通じて日本国内のみならず外国からも多くの観光客が訪れ日本を代表する観光地の一つとなっています。奈良の大仏や鹿は国際的にも有名で奈良観光のメインとなっており、修学旅行生の姿も多く見られます。東大寺修二会やなら燈花会・正倉院展・春日若宮おん祭など古都ならではの見ごたえのある行事も数多く行われます。塀・柵・門などがなく入園料も不要となっていて何時でも(365日・24時間)散策することができます。尚、旧「史蹟名勝天然紀念物保存法」に基づく名称は「名勝奈良公園」とよばれます。 |
| No20■猿沢の池 | |
 |
 |
| ■猿沢池は興福寺が行う「放生会」の放生池として、天平二一年(749年)に造られた周囲360mの人工の池です。放生会とは万物の生命をいつくしみ捕らえられた生き物を野に放つ宗教儀式とされています。風が無く晴天日には興福寺五重塔が周囲の柳と一緒に水面に映る風景はとても美しく、奈良八景のひとつとなっています。■猿沢池七不思議とは澄まず、濁らず、出ず、入らず、蛙はわかず、藻は生えず、魚が七分に水三分といわれています。猿沢池の水は澄むこと、濁ることが一度もなく、水が増すことや減ることがなく、常に一定の水量を保っています。亀はたくさんいますが、蛙がいません、何故か藻が生えないのです。毎年多くの魚が放流されているので増えるはずなのに、魚であふれる様子が無く、水より魚の方が多くてもおかしくないような池です。■釆女神社(うねめじんじゃ)は猿沢池西側のほとりにある、春日大社の末社です。言い伝えによると昔、帝の愛情が薄れたことを嘆き悲しんだ采女が池の畔の柳に衣を掛け猿沢池に身を投げました。この釆女の霊をなぐさめるために建てられたそうです。 |
 |
また、この神社は鳥居を背にした珍しい後ろ向きの社である。最初は東向きに社があったといわれている。しかし、采女の霊は我が身を投じた池を見るにしのびないと一夜のうちに社を後ろ向きにしたと伝えられています。■釆女祭の日に月の光で針に糸を通すことが出来ると願いが叶うそうです。当夜この池に手や足を浸けるとシモヤケにかからないともいわれている。 |
| No21■開化天皇(カイカテンノウ)陵 |
 ■春日川坂上陵(かすがのいざかわのさかのえのみささぎ)は開化天皇の墓とされています。この陵は念仏寺山古墳といわれ全長約100メートルの前方後円墳です。開化天皇は孝元天皇の第二皇子であり『古事記』『日本書紀』に記される第九代天皇です。稚日本根子彦大日日尊(ワカヤマトネコヒコオオビビノミコト)『古事記』では若倭根子日子大毘々命とよばれています。また開化天皇の皇居は春日率川宮といわれ近隣の率川神社、近辺に宮があったと伝えられています。 ■春日川坂上陵(かすがのいざかわのさかのえのみささぎ)は開化天皇の墓とされています。この陵は念仏寺山古墳といわれ全長約100メートルの前方後円墳です。開化天皇は孝元天皇の第二皇子であり『古事記』『日本書紀』に記される第九代天皇です。稚日本根子彦大日日尊(ワカヤマトネコヒコオオビビノミコト)『古事記』では若倭根子日子大毘々命とよばれています。また開化天皇の皇居は春日率川宮といわれ近隣の率川神社、近辺に宮があったと伝えられています。 |
| No22■平城京跡(へいじょうきょうあと)【世界遺産】 |
 |
| ■平城京は和銅三年(710年)から延暦三年(784年)までの奈良時代の都です。藤原京からの遷都は慶雲四年(707年)に始まり、和銅一年(708年)には元明天皇が律令制にもとずいた政治をおこなう中心地として飛鳥に近い藤原京から都を移したのです。中国・唐の長安城などを模範とした都をつくることは、当時の東アジア中で国の威厳を示す意味もありました。和銅三年(710年)に遷都された時には内裏・大極殿・その他の官舎が整備された程度であり、寺院や邸宅は山城国の長岡京に遷都するまで、段階的に造営されていったといわれます。また、天平十二年(740年)聖武天皇は恭仁京へ遷都しました。これにより平城京は一時放棄されましたが天平十七年(745年)には再び平城京に遷都されました。その後の延暦三年(784年)長岡京に遷都されるまでの間、奈良の地が都として栄えました。この時期を奈良時代とよばれます。また、弘仁一年(810年)九月六日、平城太上天皇により平安京を廃し平城京へ遷都する詔が出されたが、これに対し嵯峨天皇が迅速に兵を動かし同年九月十二日、平城太上天皇は剃髪しました【薬子の変】。これにより平城京への遷都は実現することがなくなりました。平城京のメインストリートは京の南門である羅城門から北にまっすぐのびる幅約74mの朱雀大路です。朱雀大路をはさんで西側を右京、東側を左京といいます。左京に北の方で東にさらに張り出しがありました。 |
 |
 |
| 平城京は大小の直線道路によって、碁盤の目のように整然と区画された宅地にわけられてます。平城京の住民は四〜五万人とも十万人ともいわれているが、天皇・皇族や貴族はごく少数の百数十人程度であり大多数は下級役人や一般庶民達である。朱雀大路の北端には朱雀門が建立されていた。朱雀門は朱雀大路に向かって開く平城宮の正門であり元日や外国使節の送迎の際に儀式がおこなわれたほか、都の男女が集まって恋の歌をかけ合うのを天皇が見る、という祭りもここでおこなわれたそうです。朱雀門をくぐると天皇の住居であり、政治や国家的儀式をおこなう平城宮です。平城宮の周囲には大垣がめぐり、朱雀門をはじめ12の門がありました。平城宮の内部にはいくつかの区画があります。政治・儀式の場である大極殿・朝堂院、天皇の住まいである内裏、役所の日常的業務をおこなう曹司、宴会をおこなう庭園などです。そのなかでも政治・儀式の場は、都が一時離れた時期を境にして、奈良時代の前半と後半で大きな変化がありました。奈良時代前半に、朱雀門の真北にあった大極殿(通称、第一次大極殿)が、奈良時代後半になると東側の区画で新たに建てられたのです(通称、第二次大極殿)。これに対して、内裏は奈良時代を通じて同じ場所にありました。■これらの事実は、40年以上におよぶ発掘調査による発見です。また平城宮は他の日本古代都城の宮殿地区には例のない東の張り出し部を持ちます。この張り出し部の南半は奈良時代をつうじて「東宮」呼ばれていたようですが、孝謙・称徳天皇の時代には、特に「東院」と呼ばれていました。称徳天皇はこの地に「東院玉殿」を建て、宴会や儀式を催しました。光仁天皇の「楊梅宮」はもとより、聖武天皇の「南苑(南樹苑)」もこの場所を中心に営まれていたと考えられています。現在は東南隅に■東院庭園・南端中央に朱雀門が復原されており西北隅に平城宮跡資料館・北端中央部に遺構展示館が設けられています。■平城宮跡は、これまで二度破壊の危機に見まわれました。1961年には西南部に近鉄車庫の建設計画が持ち上がりましたが全国的な保存運動によって救われ、1963年に国道24号線のバイパス建設計画が持ち上がったときも、全国的な運動によって国道は迂回され、平城宮跡は再び破壊から守られました。ほぼ全域が特別史跡に指定され国有地として保存されています。独立行政法人奈良文化財研究所による発掘調査が進められていますが、広大な面積で調査を終えているのは3割です。全部終わるにはまだ百年はかかると言われています。京都に遷都されて以後百年も経ないうちに田畑となりましたが、地中に奈良時代の遺構・遺物が取り残されました。奈良市で一番低い地形が幸いして水位が高く、土中にある木簡などが風化せず墨跡もあざやかなまま保存されています。■平城宮・京の研究は幕末の北浦定政に始まります。それ以来篤志家達の保存運動は細々とされてきましたが、国が本格的調査に乗り出したのは1959年だそうです。木簡が平城宮跡で最初に発見されたのは1961年です。その時出土した39点の木簡は2003年3月に重要文化財指定の等身を受けました。その後に全国で22万点を越える木簡が見つかり7万点が平城宮跡で見つかりました。続日本紀などの古記録に書かれている記述が木簡で裏打ちされたり、記述にはない内容が解析されるそうです。平城京跡は埋蔵文化財として1998年に世界遺産に指定されました。 |
 |
| No23■平成天皇(ヘイゼイテンノウ)陵 |
 |
■第五一代平城天皇陵は楊梅(やまもも)陵とよばれています。平城天皇は都が平安京へ遷都されたが安殿親王の頃の平城京が懐かしく思い、天皇譲位後に不退寺に移り住み奈良で亡くなりました。楊梅陵は五世紀に造営された全長約250mの前方後円墳。別名は市庭(いちにわ)古墳とよばれます。平城宮造営時に前方部が破壊され周濠も埋められていて現在では円墳となっています。 |
| No24■仁徳天皇皇后 磐之媛命(イワレノヒメミコト)陵 |
 ■平城天皇陵の近くに佐紀丘陵があり、この丘陵に佐紀盾列(たてなみ)古墳群があります。中の一つが仁徳天皇の皇后である磐之媛を葬った磐之媛命陵です。周濠をめぐらす大きな前方後円墳。磐之媛は葛城豪族の娘です。当時、天皇は八田皇女を妃に迎えようとした。この事に怒り、皇后は天皇宮を出られ山城筒城宮で暮らされたそうです。その後、難波宮に帰ることなく仁徳三五年(347年)この宮で崩御しました。悲しい嫉妬に苦しみながらも天皇を愛しみました。また磐之媛命は優れた歌人として万葉集にも詠まれています。陵の近くには歌姫越街道が通っており磐之媛を偲んで名付けられたといわれています。 ■平城天皇陵の近くに佐紀丘陵があり、この丘陵に佐紀盾列(たてなみ)古墳群があります。中の一つが仁徳天皇の皇后である磐之媛を葬った磐之媛命陵です。周濠をめぐらす大きな前方後円墳。磐之媛は葛城豪族の娘です。当時、天皇は八田皇女を妃に迎えようとした。この事に怒り、皇后は天皇宮を出られ山城筒城宮で暮らされたそうです。その後、難波宮に帰ることなく仁徳三五年(347年)この宮で崩御しました。悲しい嫉妬に苦しみながらも天皇を愛しみました。また磐之媛命は優れた歌人として万葉集にも詠まれています。陵の近くには歌姫越街道が通っており磐之媛を偲んで名付けられたといわれています。 |
| No25■垂仁天皇皇后 日葉酢姫(ヒバスヒメ)陵 |
 ■日葉酢媛命陵は狭木之寺間陵(さきのてらまのみささぎ)とよばれます。第十一代垂仁天皇の皇后。日葉酢姫陵が崩御された時、殉死の風習を止めるため相撲の始祖といわれている野見宿禰(のみのすくね)の提案により土師に埴輪を造らせ皇后の陵側に立てたと伝えられています。こうして日葉酢姫の陵に初めて埴輪が登場したと伝えられています。また野見宿禰の功績により土師氏(はじし)という名前を天皇より賜ったそうです。この時以降、天皇の喪葬を司る役目を果たしたといわれます。また日本書紀によると垂仁天皇の皇后は沙本毘売命(サホヒメノミコト・狭穂姫)です。沙本毘売命は心優しい皇后であったが自分の兄の沙本毘古王(サホビコノミコト)操られ天皇を暗殺しょうとしたのです。結果自害を迫られました。その前に自分の代わりにと異母兄の丹波道主命(タニワミチヌシノミコト)の五人の娘(日葉酢媛命・渟葉田瓊入媛(ヌハタニイリヒメ)・真砥野媛(マトノヒメ)・薊瓊入媛(アサミニイリヒメ)・竹野媛(タカノヒメ)を天皇の妃にしています ■日葉酢媛命陵は狭木之寺間陵(さきのてらまのみささぎ)とよばれます。第十一代垂仁天皇の皇后。日葉酢姫陵が崩御された時、殉死の風習を止めるため相撲の始祖といわれている野見宿禰(のみのすくね)の提案により土師に埴輪を造らせ皇后の陵側に立てたと伝えられています。こうして日葉酢姫の陵に初めて埴輪が登場したと伝えられています。また野見宿禰の功績により土師氏(はじし)という名前を天皇より賜ったそうです。この時以降、天皇の喪葬を司る役目を果たしたといわれます。また日本書紀によると垂仁天皇の皇后は沙本毘売命(サホヒメノミコト・狭穂姫)です。沙本毘売命は心優しい皇后であったが自分の兄の沙本毘古王(サホビコノミコト)操られ天皇を暗殺しょうとしたのです。結果自害を迫られました。その前に自分の代わりにと異母兄の丹波道主命(タニワミチヌシノミコト)の五人の娘(日葉酢媛命・渟葉田瓊入媛(ヌハタニイリヒメ)・真砥野媛(マトノヒメ)・薊瓊入媛(アサミニイリヒメ)・竹野媛(タカノヒメ)を天皇の妃にしています |
| No26■第十三代成務天皇(セイムテンノウ)挟城盾列池後(さきのたたなみのいけじり)陵 |
 ■成務天皇は第十二代景行天皇の第四皇子で名を稚足彦天皇(わかたらしひこのすめらみこと)と云い景行天皇五一年八月四日(121年9月3日)に立太子、成務天皇元年(131年)正月に即位した。日本書紀によれば成務三年(133年)に武内宿禰を大臣とし、成務五年(135年)九月に初めて地方の国県の区画を定め国郡(こおり)県(あがた)邑(むら)のそれぞれに定め首長を置き地方行政機構の整備を図ったと伝えられています。これにより人民は安住し天下太平であったという。これらは『古事記』にも大同小異で「建内宿禰を大臣として大国・小国の国造を定めたまひ、また国々の堺、また大県小県の県主を定めたまひき」とあり『先代旧事本紀』の「国造本紀」に載せる国造の半数がその設置時期を成務朝と伝えていることも注目されています。四八年三月一日(178年4月5日)に甥の足仲彦尊(後の仲哀天皇)を皇太子に立て六十年(190年)六月に崩御107歳です。『古事記』では95歳と記されています。日葉酢媛命陵・称徳天皇陵とともに『佐紀三陵』と言われます。 ■成務天皇は第十二代景行天皇の第四皇子で名を稚足彦天皇(わかたらしひこのすめらみこと)と云い景行天皇五一年八月四日(121年9月3日)に立太子、成務天皇元年(131年)正月に即位した。日本書紀によれば成務三年(133年)に武内宿禰を大臣とし、成務五年(135年)九月に初めて地方の国県の区画を定め国郡(こおり)県(あがた)邑(むら)のそれぞれに定め首長を置き地方行政機構の整備を図ったと伝えられています。これにより人民は安住し天下太平であったという。これらは『古事記』にも大同小異で「建内宿禰を大臣として大国・小国の国造を定めたまひ、また国々の堺、また大県小県の県主を定めたまひき」とあり『先代旧事本紀』の「国造本紀」に載せる国造の半数がその設置時期を成務朝と伝えていることも注目されています。四八年三月一日(178年4月5日)に甥の足仲彦尊(後の仲哀天皇)を皇太子に立て六十年(190年)六月に崩御107歳です。『古事記』では95歳と記されています。日葉酢媛命陵・称徳天皇陵とともに『佐紀三陵』と言われます。 |
| No27■仲哀天皇 神功皇后(ジングウコウゴウ)陵墓 |
 ■神功皇后陵墓は古事記によると「御陵在沙紀之盾列池上陵(御陵は沙紀の盾列池上陵・さきのたたなみのいけがみのみささぎに在り」日本書紀では「葬狭城盾列陵(狭城盾列陵・さきのたたなみのみささぎに葬る」と記されています。狭城盾列陵とは佐紀盾列古墳群のことです。承和十年(843年)盾列陵で奇異があり調査の結果、神功皇后陵・成務天皇陵を混同していたという記事が『続日本後紀』にありました。後に「御陵山」と呼ばれていた佐紀陵山古墳(現日葉酢媛陵)が神功皇后陵とみなされ神功皇后の神話での事績から安産祈願に霊験があるとして多くの人々が参拝していた。その後、西大寺において「京北班田図」が発見され文久三年(1863年)五社神古墳が神功皇后陵に治定されました。神功天皇は日本書紀などによると201年〜269年までの間、政事を執りおこなったとされている。夫である仲哀天皇の急死(200年)後に住吉大神の神託により、お腹に子供(応神天皇)を妊娠したまま海を渡り朝鮮半島に出兵しました。新羅の国を攻めましたが新羅は戦わずして降服し朝貢を誓いました。高句麗・百済も朝貢を約したと言われている三韓征伐を成し遂げた。渡海の際、お腹に月延石・鎮懐石と呼ばれる石をあてサラシを巻き冷やすことにより出産を遅らせたと言われます。この月延石は三個あると言われており長崎県壱岐市・京都市の月読神社・福岡県二丈町の鎮懐石八幡宮に奉納されたと伝えられます。三韓征伐の帰路において筑紫の宇美で応神天皇を出産し志免でお紙目を代えたと伝えられています。他に壱岐市の湯ノ本温泉で産湯をつかったなど九州北部に数々の伝承が残っており九州北部に縁の深い人物であったと言われます。また神功皇后の皇子(応神天皇)に異母兄にあたる香坂皇子・忍熊皇子がいます。この二人の皇子が畿内で反乱を起こし戦いを挑みましたが神功皇后軍は武内宿禰・武振熊命の働きによりこれを平定したといわれています。この時代は長期間にわたり天皇が空位のままであり明治時代以前は神功皇后を天皇(皇后の臨朝)とみなし十五代の帝と数えられていましたが大正十五年(1926年)十月の詔書により歴代天皇から外されました。神功皇后は卑弥呼と同じような巫女王とする見方もあり住吉三神と共に住吉大神の一柱とし、また応神天皇と共に八幡三神の一柱として信仰されるようになりました。大分県の宇佐神宮・大阪府大阪市の住吉大社・福岡県福津市の宮地嶽神社・福岡県大川市の風浪宮など幾つかの神社の祭神となっており福岡市の香椎宮や筥崎宮・福岡県宇美町の宇美八幡宮・壱岐市の聖母宮でも祀られています。 ■神功皇后陵墓は古事記によると「御陵在沙紀之盾列池上陵(御陵は沙紀の盾列池上陵・さきのたたなみのいけがみのみささぎに在り」日本書紀では「葬狭城盾列陵(狭城盾列陵・さきのたたなみのみささぎに葬る」と記されています。狭城盾列陵とは佐紀盾列古墳群のことです。承和十年(843年)盾列陵で奇異があり調査の結果、神功皇后陵・成務天皇陵を混同していたという記事が『続日本後紀』にありました。後に「御陵山」と呼ばれていた佐紀陵山古墳(現日葉酢媛陵)が神功皇后陵とみなされ神功皇后の神話での事績から安産祈願に霊験があるとして多くの人々が参拝していた。その後、西大寺において「京北班田図」が発見され文久三年(1863年)五社神古墳が神功皇后陵に治定されました。神功天皇は日本書紀などによると201年〜269年までの間、政事を執りおこなったとされている。夫である仲哀天皇の急死(200年)後に住吉大神の神託により、お腹に子供(応神天皇)を妊娠したまま海を渡り朝鮮半島に出兵しました。新羅の国を攻めましたが新羅は戦わずして降服し朝貢を誓いました。高句麗・百済も朝貢を約したと言われている三韓征伐を成し遂げた。渡海の際、お腹に月延石・鎮懐石と呼ばれる石をあてサラシを巻き冷やすことにより出産を遅らせたと言われます。この月延石は三個あると言われており長崎県壱岐市・京都市の月読神社・福岡県二丈町の鎮懐石八幡宮に奉納されたと伝えられます。三韓征伐の帰路において筑紫の宇美で応神天皇を出産し志免でお紙目を代えたと伝えられています。他に壱岐市の湯ノ本温泉で産湯をつかったなど九州北部に数々の伝承が残っており九州北部に縁の深い人物であったと言われます。また神功皇后の皇子(応神天皇)に異母兄にあたる香坂皇子・忍熊皇子がいます。この二人の皇子が畿内で反乱を起こし戦いを挑みましたが神功皇后軍は武内宿禰・武振熊命の働きによりこれを平定したといわれています。この時代は長期間にわたり天皇が空位のままであり明治時代以前は神功皇后を天皇(皇后の臨朝)とみなし十五代の帝と数えられていましたが大正十五年(1926年)十月の詔書により歴代天皇から外されました。神功皇后は卑弥呼と同じような巫女王とする見方もあり住吉三神と共に住吉大神の一柱とし、また応神天皇と共に八幡三神の一柱として信仰されるようになりました。大分県の宇佐神宮・大阪府大阪市の住吉大社・福岡県福津市の宮地嶽神社・福岡県大川市の風浪宮など幾つかの神社の祭神となっており福岡市の香椎宮や筥崎宮・福岡県宇美町の宇美八幡宮・壱岐市の聖母宮でも祀られています。 |
| No28■稱徳天皇(ショウトクテンノウ)陵 |
 ■福第四八代稱徳天皇高野陵(しょうとくてんのう たかののみささぎ)は佐紀古墳の中ではやや小形の古墳です。他の佐紀古墳群の主軸としては何れも南北方向に対し稱徳天皇陵は、やや東西方向を向いています。逢拝所は西から東向きになっています。また稱徳天皇は聖武天皇の第二皇女(阿倍内親王・高野姫尊)で奈良朝六代目の天皇とされ天平感宝元年・天平勝宝元年(749年)に父聖武天皇の譲位を受けて即位し第四六代孝謙天皇となりました。天平勝宝4年(752年)には東大寺大仏の開眼の供養を行い受戒して法基と称した。天平宝字二年(758年)には大炊王(淳仁天皇)に譲位したが不和となり天平宝字八年(764年)淳仁天皇を擁立庇護し道鏡を除こうとした太政大臣藤原仲麻呂(恵美押勝)を越前国に追い途中の近江国勝野鬼江で捕らえ妻子もろとも斬殺した恵美押勝の乱である。この後、淳仁天皇を廃し一度位を退いたものの再び天皇に戻る重祚(ちょうそ)し第四八代稱徳天皇となりました。在位中には弓削道鏡を登用して寵愛し政治・財政の混乱を招き反感をかったが神護景雲四年(770年)に皇嗣(こうし・よつぎ)を決めないまま五三歳で崩御しました。 ■福第四八代稱徳天皇高野陵(しょうとくてんのう たかののみささぎ)は佐紀古墳の中ではやや小形の古墳です。他の佐紀古墳群の主軸としては何れも南北方向に対し稱徳天皇陵は、やや東西方向を向いています。逢拝所は西から東向きになっています。また稱徳天皇は聖武天皇の第二皇女(阿倍内親王・高野姫尊)で奈良朝六代目の天皇とされ天平感宝元年・天平勝宝元年(749年)に父聖武天皇の譲位を受けて即位し第四六代孝謙天皇となりました。天平勝宝4年(752年)には東大寺大仏の開眼の供養を行い受戒して法基と称した。天平宝字二年(758年)には大炊王(淳仁天皇)に譲位したが不和となり天平宝字八年(764年)淳仁天皇を擁立庇護し道鏡を除こうとした太政大臣藤原仲麻呂(恵美押勝)を越前国に追い途中の近江国勝野鬼江で捕らえ妻子もろとも斬殺した恵美押勝の乱である。この後、淳仁天皇を廃し一度位を退いたものの再び天皇に戻る重祚(ちょうそ)し第四八代稱徳天皇となりました。在位中には弓削道鏡を登用して寵愛し政治・財政の混乱を招き反感をかったが神護景雲四年(770年)に皇嗣(こうし・よつぎ)を決めないまま五三歳で崩御しました。 |
| No29■西大寺(さいだいじ) |
 |
 |
| ■西大寺は天平神護元年(765年)に称徳天皇の勅願により創建された真言律宗総本山の寺院です。山号は勝宝山と称しますが奈良時代の寺院には山号はなく後になって付けられたものです。この寺院は僧・常騰(じょうとう)を初代住職として建立され南都七大寺の1つとして奈良時代には壮大な伽藍を誇っていたが平安時代に一時衰退し、鎌倉時代に興正菩薩叡尊(こうしょうぼさつえいそん)により復興されました。現在の本尊は釈迦如来です。その建立当時は恵美押勝の乱平定を祈願し孝謙上皇(称徳天皇)が造立した金び銅四天王像を安置しています。この四天王像は西大寺四王堂に今も安置されていますが増長天像が足元に踏みつける邪鬼だけが創建当時のものであり他の像は本体も後世の作か補作と言われています。また西大寺の寺名は言うまでもなく大仏で有名な東大寺に対するものであり創建時は薬師金堂・弥勒金堂・四王堂・十一面堂・東西の五重塔などが立ち並ぶ壮大な大伽藍を有していました。しかし平安時代に入って衰退し火災・台風などにより多くの堂塔が失われ寺は興福寺の支配下に入っていました。その後、西大寺の中興の祖となったのは鎌倉時代の僧・叡尊(興正菩薩1201〜1290)です。叡尊は建仁元年(1201年)大和国添上郡(大和郡山市)に生まれました。十一歳の時から醍醐寺・高野山などで修行し文暦二年(1235年)三五才の時に初めて西大寺に住しました。後に一時、海龍王寺に住し嘉禎四年(1238年)西大寺に戻りました。叡尊は九十才で没するまで約五十年以上、荒廃していた西大寺の復興に尽くし当時の日本仏教の腐敗・堕落した状況を憂い戒律の復興に努めました。また貧者・病者などの救済(社会福祉事業)に力を尽くしました。この西大寺に現存する仏像・工芸品などには本尊釈迦如来像をはじめ叡尊の時代に制作されたものが多くあります。その後も忍性などの高僧を輩出するとともに荒廃した諸国の国分寺の再興に尽力し南北朝時代の明徳二年(1391年)に出された「西大寺末寺帳」には八ヶ国、同時代のその他の史料から更に十数ヶ国の国分寺が西大寺の末寺であったと推定されています。 |
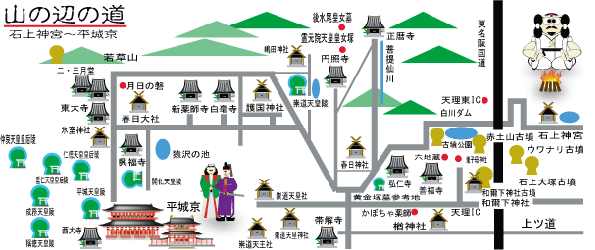 |